
「Society 5.0でもアナログが大切」ヘルスケア事業を展開する関社長が考える未来

会社概要
- 会社名
- アルスタクリエイト株式会社
- 代表者名
- 代表取締役社長 関 良一
- 所在地
- 東京都墨田区京島1丁目33−13
- 創業
- 2024年7月1日
- 会社HP
- https://www.arusta.co.jp/
デジタル化が進み、オンラインショッピングが主流になった現代。薬局は、リアルな顧客接点をどう維持するかという大きな課題に直面しています。
そんな中、アルスタクリエイト株式会社は、健康習慣を促進するスタジオ「アルスタ」や、下肢筋力測定器「ロコモスキャンG」のレンタルサービスを通じて、新しい形のサービス提供を開始しました。
2024年7月に医療機器の製造・販売を行うオルトモスホールディングス株式会社の子会社としてスタートしたこの企業は、独自のアプローチで注目を集めています。
本記事では、アルスタクリエイト株式会社 代表取締役社長 関 良一さんにインタビューを行い、新規事業の背景や目指す未来、そしてなぜ社長業を続けるのかについてお話を伺いました。
薬局にはリアルな顧客接点が必要。新規事業から考える未来
── 健脚習慣スタジオ「アルスタ」は、どのような経緯で始められたのでしょうか?
一部の薬局ではQRコードを読み取るだけで自宅に薬を配送するサービスを提供しています。今後、こうしたサービスはさらに広がっていくでしょう。
しかし、そうなると薬局は、リアルな顧客接点をどこで持つのかが課題となります。その解決策のひとつとして、運動教室の運営をスタートしました。
── 他社ですが、健康管理のカフェを始めた薬局もありますよね。それも同じ理由なのでしょうか。
そうですね。薬局もビジネスなので、来店がなければ商売が成り立ちません。店舗に来てもらうための、何らかのタッチポイントを求めている企業は多いと思います。
今は、Amazonや他のECサイトで薬が簡単に購入できる時代です。そのため、顧客をオンラインに奪われる前に対策を講じなければいけません。
特に、高齢者やデジタルリテラシーが低い人、ネット通販に完全に移行しておらず、薬局に足を運んでくれる可能性の高い人たちとリアルな接点を持つことが大切です。そのために、現在、運動教室を含めた事業設計を進めています。
── 薬局は、AmazonやECサイトがライバルなんですね。
あとは、ドラッグストアもライバルです。ドラッグストアは、言ってしまえばスーパーのいいとこ取り。薬、食品、いろいろな物が買えるから、生活するうえで便利ですよね。便利なところに人が流れるので、こうした企業もライバルになります。
── 「アルスタ」の競合はありますか?
ビジネスではなく、ボランティアベースで似たような取り組みを行う団体はあります。それに、薬局に足を運ぶ人が減ってきたこともあり、従業員を使って「空いている時間に何かやってみたい!」と考えている会社はたくさんあるので、今後増えていくかもしれません。
しかし、弊社には「筋力測定器」という、競合に対する優位性があります。
── 筋力測定器が優位性になるのですか?
弊社の「筋力測定器」は、短時間で正確に測定できるという強みがあります。
解剖学的に見ると、人間の体で最も大きな筋肉は太ももです。この太ももを鍛えることで、筋力が向上しやすく、効果も出やすくなる。そのため、この部位をターゲットにした運動プログラムを提供し、「筋力測定器」を用いることで、成果を素早くかつ定量的に測定できる競合優位性を活かし、事業全体を設計しています。
── 測定器はもともとBtoB向けに作っていたものですか?
医療機関向けに、リハビリ効果の検証用として提供していました。でも、日本国内の病院数は約1万件と限られています。100万円程度の機器を1万台販売すれば市場が飽和してしまい、なかなか次を買ってもらえない。
じゃあ、「次にどう展開するべきか?」という視点で新規事業を考えて、現在のビジネスにたどり着きました。
身近な人がハンディキャッパーに。医療業界を目指し、社長を引き受けた理由
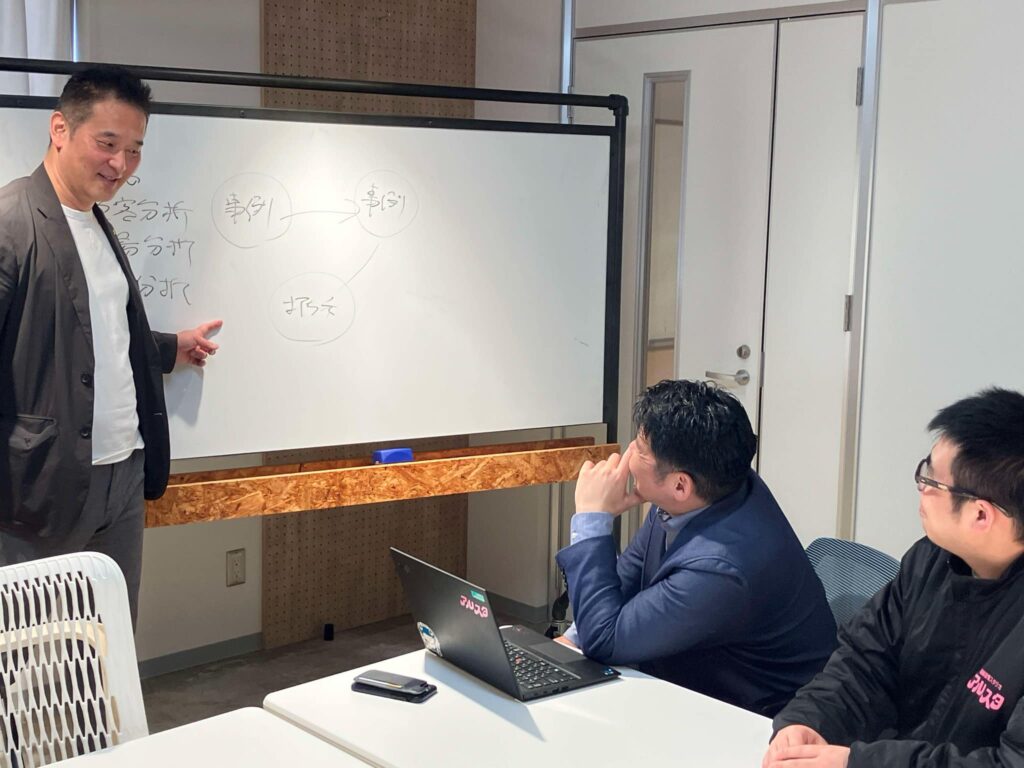
── 関さんのご経歴や、新規事業に携わり続けている理由について教えてください。
新卒で現在の会社に入社して、営業成績が良かったので早くからマネージャーになりました。次は営業部長になるかと思っていたのですが、予想外に、新規事業部へ移動することになりました。
当時は、それが評価されての異動だと気づかず、「左遷された」と思いました……。
── 医療関係のご出身ではないですよね?
全く違います。大学時代は成績ギリギリで、六本木や渋谷、新宿にいることの方が多かったです(笑)。卒業できたのは奇跡だと友人に言われました。
── そんな中で、どうして今の会社に就職を?
母が私を出産した際に股関節を負傷し、ハンデキャッパーになってしまったんです。私は、生まれたときに母親の歩行能力を奪ってしまったと思いました。
その経験から、歩行機能の改善に関わるビジネスがしたいと、ずっと思っており、今の会社に就職しました。
── 関さんは、社長になりたいと思っていましたか。
うーん、正直「なりたい」と思っていたわけではありません。社長になるという話が出たときも、引き受けるかどうか悩みました。
営業時代、会社を辞めようと思ったときに、「俺はお前の会社に世話になったと思っているから、お前の世話もしてきた」「お前がこの会社をもっと良くしてくれると思ったから、お前の成長を助けた」みたいなことを、何人もの仲の良い医者や取引先の社長から言われたことがあったんです。この経験も大きかったですね。
まだ自分というブランドがない時代に、会社があったから育ててもらえた。だから恩返しをしないと、という思いがありました。
── 過去に、転職を考えたんですね。
実は、新卒半年でヘッドハンティングの話がありました。その後も何度も声をかけられましたし、収入を増やしたいと考えて転職を検討したこともあります。実際、辞表を書いて提出したこともありました。
しかし、会社を辞めようとしたタイミングで、お世話になった社長の奥さんが亡くなって、葬儀に参列することになったんです。
そこで、喪主である社長に「辞めようと思います」と言いました。そうしたら、「バカ野郎!」って怒鳴られたんですよ。
── 葬儀の場で?
そう。500人くらい参列者がいたのに、喪主がガチギレ(笑)。
「お前の会社には世話になったし、お前にも期待していたのに、恩返しもせず辞めるのか!」と。周囲はドン引きしていましたよ。すごく恥ずかしかった。でも、そんな気持ちでこの人は私にかかわってくれたのかと思うと、なんか涙が止まらなくて。
そんなこともあって、結局、会社に残りました。自分の奥さんの葬式で、あそこまで感情的になるって、よほどの思いがないとできないと思うんです。「この人たちのために頑張ろう」という気持ちになりました。
これは、32~33歳くらいのときでしたね。
── そうした経験もあって、会社に残ろう、社長を引き受けようという思いにつながっていったんですね。
そうですね。今はその方の息子や孫が会社を継いでいるけど、当時みんな参列していたので「あの人は前社長が期待していた人だ」っていう目で見られるんですよ。だから余計に、頑張らないとなって思います。
── そんなエピソードがあったら、気軽に辞めようとは思えませんね。
それだけじゃなくて、社内でも同じようなことがあったんです。
辞表を出したときに、うちの事業部長が「来い」と言って、私を豊洲のガンセンターに連れて行きました。当時は伏せられていたのですが、営業の取締役がガンを患っていたんです。
病棟の中を歩いていたら、遠くにいる人が、明らかに私に向かって怒鳴っている。近づいていくと、それが取締役で。「これから、この会社はお前中心で回って行くのがわかんねえのか!そのために今まで雇ってたんだ!」って、30分くらい怒鳴られました。
辞表が承認されるかどうかというタイミングで、たまたま葬式があって怒鳴られるし、取締役に会いに行ったらガンでガリガリに痩せていて、大声も出せないだろうって状況で怒鳴ってくる。辞められねえ、って思いますよね。
── 葬式で怒鳴られ、病院でも怒鳴られ。めったにない経験ですね。
本当に(笑)。辞表を出したら会社の上司にも、取引先の世話になった社長にも怒鳴られるって、そんなことある!?っていう。
2人とも「会社を変えていくのはお前なんだ」って言うんです。当時は仕事を一生懸命やっていたけど、自分が会社を変える人間とは思っていませんでした。縁故で採用されたわけでもないし。
実は、あとになって人事の人と飲みに行く機会があって。「僕って会社でどういう扱いだったんですか?」と聞いたら、「お前は入社当時から経営者候補として期待されてた」と言われたんです。「なんで本人に言わなかったんですか?」と聞いたら、「言ったら調子に乗るだろ」って!
営業が100人以上いる会社で、毎年何人も採用しているのに、まさか自分がそんな期待をされていたとは思いませんでした。実績は出していたけど、誰も優しくしてくれなかったし(笑)。だから、話を聞いたときは驚きました。
── 辞めようとまで思っていたのに「実は経営者候補」と言われたら驚きますね。
結局、先代の社長から「新規事業を起こしたいから協力してくれ」と言われて、通販事業を1年半で立ち上げることになりました。今は軌道に乗り、売り上げも利益も伸びています。
ヘルスケア開発の裏側。論文化と検証で健康被害を防ぐ

── サービスは全て論文化されているという話を伺ったのですが本当ですか?
本当です。たとえば、弊社が運営する体操教室「アルスタ」の体操にも論文があります。
体操というサービスを提供するにあたり、「半年間、一定の頻度で介入すると、これくらいの改善効果がある」という内容をすべて論文化しました。
一般的な体操教室では、提供するプログラムの効果を論文化していません。しかし、弊社では先に論文化を済ませて、「だからこれをやります」と有効性が証明された状態でサービスを展開しています。
── 一般的なフィットネススタジオでは、論文化するのは難しいのでしょうか。
弊社では医師と共同でメニューを考え、効果測定を行い、論文化まで進めています。これができるのは、親会社が医療機器の開発をしていたバックグラウンドがあり、信頼できる医師とのネットワークがあるからこそです。
一般的なフィットネススタジオでは、こうした下地がないため、論文化は難しいかもしれません。
── 論文化するにはどのくらい時間がかかりますか。
論文化にはまず、学会に「こういう研究結果があります」と文章を提出する必要があります。そうすると「ここがダメ」という指摘が返ってくる。それを直して、また提出して、という作業を何度も繰り返しながら完成させていくため、論文化には1年~1年半ほどかかります。
医療機器で簡単にエラーが出たらマズイので、想像上の「こんなものができました」だけではなくて、実際に臨床現場で使って、事故が起きないかなどの検証も行わないといけません。
── 事故が起きたら一発アウトな世界ですよね。
そうです。また、体操教室で行う運動は、病院で使う医療機器とは責任の所在が異なります。
医療機器の場合、事故が起きた際の責任は医師にあります。しかし、ヘルスケア用品の場合、責任は提供する弊社側にあります。だからこそ、責任を担保するためにより慎重な検証が必要になるんです。事故や健康被害が出ては取り返しがつきません。
── 関さんは健康被害を防止するために、神奈川県でヘルスケアの勉強会も開かれているんですよね。
神奈川県の取り組みのひとつですね。行政からの依頼で、企業担当者を育成する事業を私が引き受けています。
── 具体的にどのようなことを教えているのでしょうか。
例えば、「木を食べたら健康になった」という海外論文を見た人が「商品化して売りたい」と相談してくるので、その際に「検証しないと世には出せません」ということを教えています。
「え、本当に!?」と思うような相談も多いんですよ(笑)。自分で確認せず、本当かどうかわからない話をうのみにしてしまう人は意外にたくさんいます。そういった人に基礎的な知識を教えているんです。
── 健康にかかわる分野だと、製品化が難しそうなイメージがあります。一歩間違えれば、大事件につながりかねません。
以前はヘルスケア業界の規制が緩かったんですが、放置した結果、死者を出すような大きな健康被害事件が発生しました。そのため、最近は規制が厳しくなっています。
── ちなみに、ヘルスケア開発にかかわるなら知っておいてほしい、という内容はありますか?
たくさんありますよ。例えば、ヘルスケアプロダクトを開発するなら、
- 試作開発
- 予察実験
- 研究計画
- 実証実験
- 学会発表
- 論文化
という流れが必要です。全部やれとは言いませんが、本来ならすべてやるべきことなんです。あとは、法的規制とか科学的妥当性とか、エビデンスにはレベルがあって、どこまでエビデンスって作らなきゃいけないのかとか。
── 学ぶことも、やることも多そうですね。
そうですね。でも、健康被害が出て損害賠償を支払うことになったら、もっと大変なことになります。
私は経済学部出身ですが、医療業界に長年関わり、自分で医学論文を書いた経験もあります。その経験も活かして、まったく知識がない人にも分かりやすく教えています。
── ちなみにお金はいただいているんですか?
もらっています。でも安いですよ。
私が求めているのは、お金よりも肩書きや人との出会い。面白い人と協業できて、公的な立場で指導している肩書きが得られるのは大きなメリットです。勉強会にはそうした価値があるから、積極的に引き受けています。
「人間臭さが大切」Society 5.0の世界でヘルスケアはどうなる?

── 関さんが考える会社のビジョンやヘルスケアの未来についてお話を伺いたいと思います。
私は、Society 5.0の世界を前提に、ビジョンを考えています。そして、その世界で最終的にデジタルというものは、瞬間風速的に起こるものと、リアルとデジタルが融合して始まるもの、両方があると思っています。
そうなったとき、ヘルスケアはどうなるのか。
私は、アプリケーションを使ってログやデータを使い、健康をケアしていくデジタル的なものと、白衣を着た人たちから「良くなってますよ、頑張ってますよ」と言われるアナログ的なものが残ると思っています。
── 関さんが運営されている健脚習慣スタジオは、どちらかというとリアル(アナログ)なヘルスケアですよね。
そうですね。技術が発達しても、リアルのヘルスケアは大切だと思います。デジタルのヘルスケアを否定しているわけではありませんし、デジタル慣れした若い世代は、全部デジタル化されても問題ないかもしれません。でも、一部の人にはリアルでアナログな手段も必要だと思うんです。
── アナログのヘルスケアとは、例えばどういうことを指すのでしょうか?
例えば、「ちゃんと生活習慣を変えて、体調も良くなったね」と言われることです。行動に対して、こうしたフィードバックを求める人は多いのではないでしょうか。
介護やリハビリテーションはロボットで代用できるかもしれません。しかし、最後は人間から「頑張ったね」と言われることが何より大切だと感じています。
ヘルスケアは、人との交流によって生まれる、人間らしいぬくもりが重要だと思うんです。このぬくもりがあるからこそ、つらい生活改善を頑張ろうと思える。そして、この「温度感」は、対人コミュニケーションだから得られるものだと考えています。
── 確かに、人の温かさは必要かもしれません。
人が生きるため、健康維持のために必要なのは、白衣を着た人とのコミュニケーションだと思います。ロボットでは、人間の承認欲求を満たせないでしょう。
私自身、高齢者になって健康を維持しているときに、「頑張ったね」という言葉は、人間からもらいたいです。
── それは年齢的な影響もあるのでしょうか?例えば、若い世代なら、そこまで人間らしさを重視しないかもしれません。
関係はあるかもしれません。年齢というよりも、生活環境、ライフステージなど、いろいろな原因がありそうです。
例えば、子どもができて、必死に育児をしている人がAIに「頑張ったね」と言ってもらいたいか、人間に言ってもらいたいかと考えたら、人間ではないでしょうか。
私はデジタル化が進んでも、人とのコミュニケーションは残っていくと考えています。
── 年齢やライフステージによって、求めるコミュニケーションは変わりそうですね。
変わりますね。例えば、ちょっと前に、クラブハウスというSNSが流行りましたよね。あれって今、どうなっているか知っていますか?
── クラブハウスというと、音声SNSですよね。すぐに廃れてしまった印象があります。
クラブハウスは、現在日本のマタニティSNSとして残っているんです。私はこれを知ったとき、とても驚きました。
日本では深夜、夜泣きに悩んで、孤独に育児をしている人が、クラブハウスに集まっているんです。夜泣きが大変でどうしようもないけど、クラブハウスでお互いがつながっているから、この時間も一人じゃない、みたいな。
これを聞いたときに、人間クセー!って思いました。クラブハウスってそういう使い方があったのか!って。
そして、やっぱり、最終的に人間臭いものが残るんだなと思ったんです。
── 面白い事例ですね!音声SNSには、そんな使い方もあるのか……。
クラブハウスってちょうど良いですよね。周囲が寝静まっていて、孤独に子どもの世話をしている時間に、相手が誰かわからないけど、同じ境遇の人とコミュニケーションが取れて、一人じゃないと思える。この環境はすごく良いと思います。
── 孤独解決アプリみたいになっているんですね。
そうそう!クラブハウスは孤独を解決するソリューションになっているんです。
デジタル化して、効率化していくのは良いと思います。しかし、こうしたアナログ面や人との交流によって生まれる暖かみは残ってほしいですね。デジタルが進むと、こうしたアナログ部分での差別化が重視されていくと思っています。
「個人の意識改革が大切」予防と投資が未来の健康を作る
── 最後に、日本のヘルスケアについて、関さんが感じる課題や改善策を教えていただけますか?
私がヘルスケアを促進しようと思う理由に、公的保険に依存している日本を、健康へ投資する社会に変えたいという思いがあります。
アメリカで盲腸の手術をすると200万円くらいかかる。でも日本は十数万円程度で済む。いざという時に安く治療を受けられることが、予防をしない原因になっているんです。
しかし、こうした社会は高齢者が増加すると維持できなくなると思います。そのときに大切となるのが、予防という概念です。
── ヘルスケアでいう予防とは、例えばどのような内容ですか?
食事、睡眠、運動など、健康を維持するための投資のことです。
生理学的に言うと、女性の体力のピークは18歳、男性は20歳といわれています。その年齢を過ぎると、体力は下降していくだけ。健康に投資をしないと悪化する一方です。
体力の低下を急激にするのか、なだらかにするのか……長く良い状態を維持したいなら、健康な習慣を作るしかありません。
─ 健康を維持するために投資をしていきましょう、と言うことですね。
そうです!ブヨブヨになって病院に通う未来より、筋肉のついたイケおじになって健康に過ごす未来よりのほうが良いですよね。
── 確かに(笑)。
お金をかけないで健康でいたいなら、運動をするしかないんです。だから私は、35歳のときに体力のピークの話を知って、剣道を始めました。
── 運動が大切だと分かっていても、なかなか実践できないんですよね……。関さんは剣道を続けて、変化を実感していますか?
やっぱり、15年前の自分の写真と見比べると見た目が変わっています。筋肉質になっていますね。ふくらはぎや腕に筋肉が付いたし、疲れにくくなったと思います。
── ヘルスケアの事業をする上でも、運動していることは大切ですね。説得力が増します。
大切ですね。実際仕事では、「このくらい鍛えなきゃだめですよ!」ってスタジオに来た人に伝えています(笑)。
ヘルスケア業界は、これからますます重要になると思います。今後、高齢化が進む中で、医療費が膨れ上がっていくのは避けられません。だからこそ、私たちは「予防」という概念をもっと広めていく必要があります。これからは病気になってから治すのではなく、健康を維持するための投資が重要になると感じています。
【編集者コメント】
テクノロジーが目覚ましい勢いで進化するSociety 5.0の時代においても、最後に人を支え、励ますのは「アナログ」であり「人間らしい温もり」――それが関社長のメッセージから強く伝わってきました。
オンラインショッピングの普及により、薬局など対面サービスの価値が見直される今、アルスタクリエイト株式会社は運動スタジオや独自の筋力測定器を活用した新規事業で“リアルな顧客接点”を創出。そこには、単なるエビデンスや研究成果にとどまらず、互いを思いやるコミュニケーションの力が生かされています。
さらに、予防と投資に目を向けるヘルスケアへの姿勢は、保険制度に頼るだけでは今後立ち行かなくなる日本社会にとって、大きな示唆となるはずです。デジタルとアナログを掛け合わせ、“人と人とのつながり”を原動力にヘルスケアを変革していく――関社長の取り組みと情熱がこれからどんな形で花開くのか、ますます注目が集まりそうです。
〈執筆=Boss Talk事務局/編集=Boss Talk事務局〉
