
【特集インタビュー】都議会議員候補(渋谷) 中村たけし氏インタビュー
渋谷から日本、そして世界へ。挑戦する人が報われる社会をつくるために
── 都議会議員候補(渋谷) 中村たけし氏インタビュー(聞き手:BossTalk編集部)
はじめに:バーでの出会いから始まったこの対談
2025年春、Boss Talkの代表 内野が新宿のバーで偶然にも新宿区議会議長/自由民主党区議会連絡協議会 の渡辺 清人氏と出会った。
Boss Talk の代表・内野は、経営者インタビューメディアのBoss Talkにて、政治家との対談を実施し、同世代に政治に興味を持ってほしい。そうでないと、我が国日本は崩壊すると。
そこで渡辺 清人氏から「渋谷に熱い男がいる」との紹介を受けたのが、中村たけし氏だ。
軽い世間話から意気投合し、その場で次回の対談が決まった。
本稿では、中村氏が歩んできた民間キャリアから政治家への転身、渋谷区で推進する多岐にわたる政策──スタートアップ支援、教育・福祉、商店街再生、インバウンド対策、環境・防災施策まで──を一挙にお届けする。
第1章|起業家の視点で描く「潤して、強くする」

1-1. 民間キャリアの原点
中村氏は新卒で大手IT企業に入社し約18年、営業・企画・グローバル展開などを経験。リーマンショックでは金融業界の混乱を肌で体感し、その後シェアオフィス大手WeWork日本法人立ち上げにも参画した。
中村氏:「20代の頃は政治が遠い存在だったが、リーマンショック時に経済と暮らしが直結することを痛感しました。企業倒産の影響は、自分の生活にも跳ね返ってくる。その危機感が、後の政治家志望につながったのです」
1-2. 政治家への転身とライフステージの変化
42歳で議員に立候補した背景には、結婚と子育ての経験があるという。
中村氏:「行政サービスやルールが子育て支援や住宅政策に深く関わると実感しました。行政を変えるには、ルールを作る側に回るしかないと考えたのです」
1-3. スローガン「潤して、強くする」の意味
- 潤す:経済を活性化し税収を増やす→教育や福祉、子育て支援に還元
- 強くする:挑戦者が安心してチャレンジできる環境を整備
中村氏:「渋谷にはすでに2000社以上のスタートアップが集積し、200を超えるシェアオフィスが稼働する“場”があります。これを行政としてバックオフィス支援や投資環境整備で後押しし、“渋谷発スタートアップ”を次の成長ドライバーに育てたい」
中村氏がビジネス最前線で培った「数字を追う視点」と、政策立案に必要な「社会への共感力」を見事に融合させている点です。
内野氏:リーマンショックの危機感やWeWorkでの経験を経て生まれた「潤して、強くする」というスローガンは、単なるキャッチフレーズに留まらず、現場の起業家に本当に寄り添う具体性を持っています。
この政策が実現することで、渋谷は挑戦を後押しする街としてさらに魅力を増し、起業家たちの成長エンジンになると確信しました。」
第2章|教育・福祉と起業支援の融合

2-1. 自治体経営は企業経営と同じ
「支出だけ増やしても持続しない。企業と同様に収入を増やすことが前提。起業支援で地域経済を潤すことが、教育無償化や介護拡充につながります」
2-2. 地域密着型起業家教育
- 学校連携:地元起業家による講演・ワークショップ
- インターン:渋谷区内スタートアップでの実地経験
「実社会を体験できる環境が、学生に起業マインドとスキルを植え付ける」
2-3. 商店街・福祉ネットワーク
商店街再生策(第3章参照)と連動し、保育園や高齢者見守りを一体化。
「買い物=コミュニティ参加。見守り機能として商店街を活用し、孤独死予防や高齢者支援の拠点にする」
内野氏:行政、教育、福祉、そして起業支援がひとつのネットワークとしてつながるビジョンには、正直言って目からウロコが落ちる思いでした。
地域の“日常の場”である商店街をハブにする発想は、単なるイベント的な福祉施策や一過性の起業支援とは一線を画します。
子どもから高齢者まで、世代を超えた交流が自然に生まれ、その中でビジネスの芽も育つ──まさに「生活と経済活動は切り離せない」という中村氏のメッセージを、肌で感じられる施策です。渋谷区がこのモデルをどこまで深化させるのか、今後の展開に大いに期待したいと思います。
第3章|渋谷の商店街をデジタルで再生—地域通貨「ハチペイ」
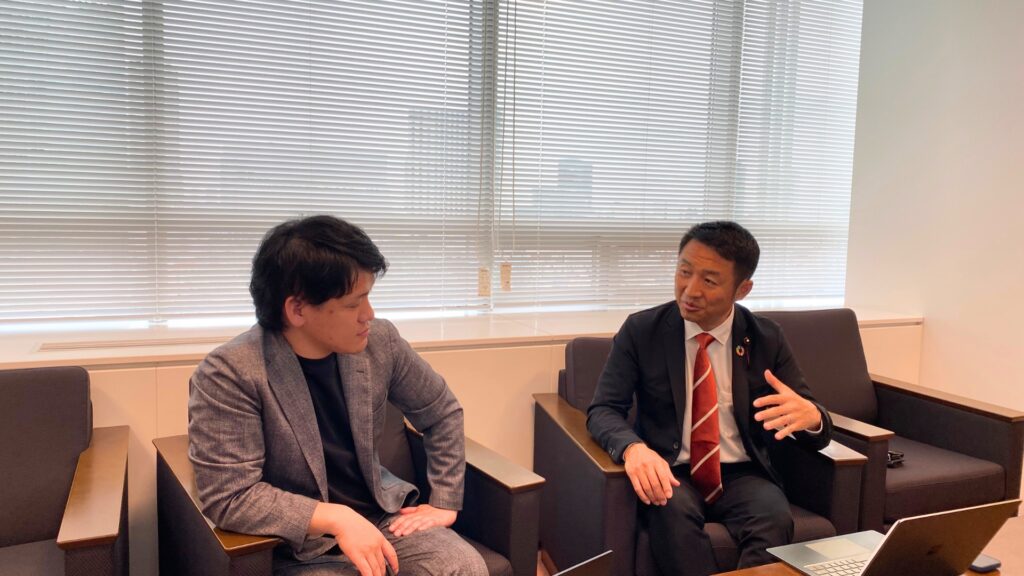
3-1. 60以上の商店街のポテンシャル
渋谷区内には60以上の商店街が存在し、地域の生活基盤を支えている。大規模再開発で消えかけた“顔の見える経済圏”を再興。
3-2. ハチペイ概要と成果
- チャージ時利得:最大50%のプレミアムポイント還元
- 決済手数料:区が全額負担(0%)
- 対象店舗:地元個人商店優先(3,000店舗以上)
導入1年で80億円超の経済効果を達成。商店街経済の活性化だけでなく、利用者の購買データを通じた需要分析にも活用。
3-3. コミュニティと見守り機能
内野氏:「高齢者の買い物頻度低下を早期に察知し、訪問支援につなげるなど、商店街が福祉インフラに機能している」。ハチペイの取り組みを知るほどに、「「デジタル」と「アナログ」」の融合がもたらす力強さに感嘆せざるをえません。
60にも及ぶ商店街が一つのアプリでつながり、個別店舗のセール情報から需要トレンドまでがリアルタイムに可視化される様は、まるで産業革命期の蒸気機関が各地を駆け巡ったかのようです。
しかも、ただの利便性向上にとどまらず、高齢者の見守りや地域コミュニティの再生といった社会的意義をも同時に実現している点に、渋谷区政の先進性を強く感じます。起業家や行政関係者だけでなく、地元住民一人ひとりが身近に実感できるイノベーションとして、全国への展開モデルとなる可能性を大いに秘めていると思います。
第4章|インバウンドと地域共存──税と条例で築くバランス

4-1. 渋谷は日本のインバウンド7割を集客
訪日客のおよそ7割が渋谷を訪問。スクランブル交差点は世界中のSNSでシェアされる観光アイコンに。
4-2. 宿泊税引き上げ提案
- 現状:100~200円/泊 → 年間44億円の税収
- 提案:1,000円またはパーセンテージ課税に引き上げ→ 10倍以上の財源確保
財源は公共スペース清掃、警備、コミュニティ支援に充当。ホノルル13.25%課税モデルを参考。
4-3. 公道カート(マリオカート型観光)の条例化
観光客向けカート事業者に対し、地元説明と誓約書提出を義務付ける条例を制定。「禁止ではなく適正運用で安心・安全の両立を目指す」
内野氏:渋谷が訪日観光客の約7割を集客しているという圧倒的な“入口”の強みを、ただ誇るのではなく、地域共存の観点から大胆に税制と条例で再設計しようという発想に驚かされました。
特に、100〜200円という“お試しレベル”の宿泊税を一気に1,000円や数%のパーセンテージ課税に引き上げる提案は、観光収益を住民サービスとコミュニティ支援に直結させる革新的な手法です。
さらに、マリオカート型観光のような新興アクティビティを禁止するのではなく、地元説明と誓約書によって「適正運用」を徹底することで、観光も地域の安心も同時に守るバランス感覚は、行政だけでなく企業や市民にも大いに参考になるでしょう。
渋谷という最先端のフィールドだからこそ実現可能な“共創モデル”として、その行方を見守りたいと思います。
第5章|人材政策と地域アイデンティティ—渋谷から日本の未来を考える

東京・渋谷──この街が次に直面するのは、少子高齢化と人口減少による労働力不足の波だ。対談の終盤で中村氏は、こうした社会構造の変化を見据えた「人材政策」について、率直な言葉で語った。
5-1. 高度人材は“積極的”に、無制限の移民受け入れには“慎重”に
「高度人材や、必要なところへの人材が、政策はありだと思いますけど、必要以上にやるっていうのはあんまり賛成はしないです」──これは、金融危機を生き抜き、シェアオフィス事業を立ち上げた民間出身の政治家らしい現実的な視点だ。
高度なスキルや専門性を持つ人材を選択的に受け入れることで、渋谷のスタートアップやデジタル施策の推進力を高める。一方で「数だけを増やせばいいわけではない」という釘の刺し方も忘れない。
5-2. 地域のアイデンティティを守るための“制限”も必要
「ただやみくもに受け入れるっていう話には絶対にならないと思うので、クルドの問題とかね。あとはその基地の周りを中国の企業に買われていいのか、という話とかあるので、やっぱりアイデンティティを持って──一定そこは、制限かけるっていうのはあるべき姿じゃないかな」──中村氏は、外国資本による不動産買収やコミュニティの希薄化への懸念も示した。渋谷らしい「まちの顔」を守りつつ、多様性を受け入れるバランス感覚がここにある。
5-3. “共生”を設計する政治の役割
渋谷は観光、起業、商店街再生と、さまざまな実験場だ。次に問われるのは、住民も訪日客も高度人材も──多様な立場の人々が互いに安心して暮らせるまちのデザインである。
中村氏: 「みんなはどう感じるんだろうな? 経営者の立場としても、移民の受け入れは必要だと思うけど、そのバランスを取るのが政治の“設計”なんです」──中村氏は、政治を「希望を設計する場」と呼んだ。
5-4. 渋谷から全国へ示す「共生モデル」
高度人材の受け入れと移住制限、観光振興と地域保全。渋谷区が描くのは、これらを両立させる「共生モデル」だ。
東京、そして日本全体が抱える人口動態の課題に対し、渋谷から発信される人材政策の答えに、私たちも耳を傾けたい。政策は机上の空論に留まらず、まちのリアルな“顔”を守りながら変革をもたらす行動計画。
その実践力が、渋谷を、そして私たちの社会を次のステージへと押し上げるだろう。
最終章|東京都議会議員選挙2025|に込める決意

「挑戦する人が報われる社会を、この渋谷から日本、世界へ広げたい」
中村氏が掲げる「7つの加速度」には、スタートアップ、商店街、インバウンド、教育、福祉、環境、防災の7つが含まれる。これらを一体化させることで、持続可能で包摂的な社会を実現するという。
中村氏:「私にとって政治は、“希望を設計する場”です。ビジョンを具体的政策に落とし込み、必ず実行していく。起業家や市民とともに作る未来を、皆さんと共有したい」
ここまで中村氏の構想を追うと、「渋谷区」というローカルな枠を超えた大きなビジョンが浮かび上がります。
7つの軸を同時並行で進めつつ、それらを相互にリンクさせるマネジメント手腕は、まさに起業家そのもの。政治家自身が“プロジェクトオーナー”となり、ステークホルダー(起業家、市民、行政など)を巻き込みながら、具体的な成果を求めている点に背筋が伸びる思いでした。
特に印象的だったのは、「潤して、強くする」という言葉。
その言葉に込められた覚悟は、どんなに困難な課題も“設計図”をもって突破しようという起業家的マインドそのものです。
選挙を控える今、中村氏の描く“渋谷モデル”がどこまで実現可能か、そしてその先にどんな新しい社会が立ち上がるのか──政策の細部だけでなく、その過程を注視していきたいと思います。
(文・BossTalk編集部)
